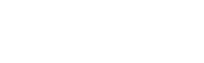General
歯が痛い・しみる
~ 一般歯科・根管治療 ~
- HOME
- 歯が痛い・しみる~ 一般歯科・根管治療 ~
歯が痛い・しみる
という症状があったら
歯や歯茎のすき間にプラーク(歯垢)が蓄積して、その中に繁殖しているむし歯菌が強い酸を出すことにより歯が溶けることをむし歯といいます。
むし歯が進行すると「歯がしみる」「歯が痛い」という症状が出始めます。
そして、それらを引き起こす要因となるのがむし歯菌、歯質、糖分、時間です。
こちらでは、東大阪・鴻池新田の歯医者「らぶ歯科医院」がむし歯の要因から進行段階、治療法までをご紹介します。
むし歯の要因は主に4つあります。
むし歯菌(細菌)
むし歯菌はプラークの中で繁殖します。
放置しておくとむし歯菌は強い酸を発して歯を溶かしてしまうので、適切なブラッシングを行って除去する必要があります。
糖 分
むし歯菌は糖分を栄養にします。糖分を消化する時に強い酸を出して歯を溶かすので、食後はブラッシングを行って口腔内をきれいにして、むし歯菌の繁殖を抑えましょう。
歯 質
生まれたときから歯質が弱く、むし歯になりやすい方もいます。特にお子様の乳歯は歯質が弱いので注意が必要です。
むし歯菌やプラークを減らすPMTCや、予防歯科を行って、口腔内環境をきれいに保ちましょう。
時 間
食後、口腔内にたまった糖分をそのままにしておくと、むし歯菌の栄養がずっと留まった状態になります。
食後すぐにブラッシングを行えば口腔内が清潔になり、むし歯になりにくくなります。
むし歯の進行段階と、対応する治療

CO 初期段階のむし歯
症 状
歯の表面がむし歯菌によって少し溶け始めた状態です。この時点では歯に穴が開いているわけではないので、自覚症状はありません。
治療方法
適切なブラッシングやフッ素塗布することで治癒が可能になります。奥歯であればシーラント(プラスチック)で歯の溝を埋めることでむし歯を予防できます。 【通院回数:1回】

C1 エナメル質が溶けた状態のむし歯
症 状
歯の表面の溶解が進行し、エナメル質が黒ずんでいる状態です。冷たい飲み物や氷などがしみるといった症状が現れます。
まだ痛みはありません。
治療方法
治療はむし歯部分を削り、被せ物でカバーしたり、詰め物を埋めたりすることで行います。 【通院回数:1~2回】

C2 象牙質まで達したむし歯
症 状
むし歯がエナメル質の内側にある象牙質まで進んだ状態です。
神経近くまで進行しているため、甘い物や冷たい物がしみたり、痛みを感じたりします。
治療方法
治療はむし歯部分を削り、被せ物や詰め物による処置を行います。
C1の状態より深く歯を削る必要があります。
【通院回数:2~3回】

C3 むし歯菌が神経に達したむし歯
症 状
むし歯菌が神経を常に刺激している状態です。患部には常に激しい痛みを伴い、日常生活に支障をきたすようになります。
治療方法
むし歯部分を削りますが、歯の大部分が失われ、進行状態によっては神経を取り除かねばなりません。根管部分の神経を取り除き、消毒して薬剤を注入する根幹治療を行った後、被せ物でカバーします。 【通院回数:2~3回】

C4 むし歯菌によって神経が壊死したむし歯
症 状
歯がむし歯菌によってほとんど解けてしまっている状態です。神経も溶かされ、死んでしまっているために痛みはなくなっているのですが、歯茎や顎の骨に膿がたまると激しい痛みを伴います。
また、膿は悪臭を発する場合があります。
治療方法
ほとんどの場合は抜歯が必要で、歯を失うことになります。
歯を抜いたら、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで歯の機能を補う必要があります。
【通院回数:2~4回】
Flow 当院で行っている検査と治療内容

Flow.01
問診表を記入し、
カウンセリングを実施
まず問診票を記入していただき、患者様の歯の状態や症状を詳細に把握します。
現在、服用している薬がある場合はお薬手帳をご持参してください。
らぶ歯科医院ではインフォームドコンセントを充実させるため、長時間カウンセリングを行っています。
患者様に寄りそったカウンセリングを行うことでより症状について詳しく把握し、治療計画に役立てることができると考えているからです。
また、プライバシーを気にされる方のために個室も完備しています。

Flow.02
レントゲン写真の撮影
肉眼では確認できないような歯の状態や形状を診察する目的で、口腔全体のレントゲン撮影を行います。

Flow.03
検査・診断
お口の状態を把握するためにさまざまな検査を行います。検査結果に伴い、患者様一人ひとりに合った治療方針をご提案します。
また、痛みや出血がある場合などは応急処置を優先して行いますので、ご安心ください。

Flow.04
歯石の除去と治療を行う
レントゲン写真や精密検査の結果に従い、適切に治療します。

Flow.05
メインテナンス(検診)
メインテナンスの時期は、治療してから2~3ヶ月後です。定期的な口腔内のクリーニングを行うことで、むし歯や歯周病にならない健康なお口を手に入れましょう。

院長からの早期発見・早期治療のススメ
むし歯は早く発見して治療することによって、歯を削ったり抜いたりすることもなくなり、健康な歯を維持できる可能性が上がります。
また、通院回数や期間も少なくなることで、患者様の体や治療費の負担も軽減。
2~3ヶ月おきに検診し、早期発見を心がけることをおすすめしています。